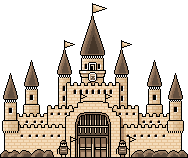<ぶらり成田>
利根川や印旛沼がある成田は
水資源が豊かで昔から川魚がよく食べられていました。
印旛沼で獲れていたうなぎもその一つ。
江戸時代になると成田山新勝寺へ参拝する成田参詣や歌舞伎鑑賞などが行楽として広まり、
参拝客をもてなすためにうなぎ料理が出されるようになったそうです。
<川豊本店>
成田山新勝寺の参道沿いにある「川豊本店」
明治時代の旅館として使われていた歴史的建造物(木造3階建ての入母屋造)の
店先で鰻がどんどんさばかれています。
評判通りの「割きたて・蒸したて・焼きたて」「フワッ・トロッ」で美味かったです。
(写真は「特上うな重」5,600円(税込)+「きも吸」200円(税込))
  
<駿河屋>
成田山新勝寺総門脇にある「駿河屋」寛政10年(1798年)創業の老舗鰻店だそうです。
備長炭で丁寧に焼かれた肉厚たっぷりのうな重(予想以上の極肉厚でした)
評判通りの「割きたて・蒸したて・焼きたて」「フワッ・トロッ」で美味かったです。
(写真は「特上うな重(肝吸付)」5,610円(税込))
  
※ 川豊・駿河屋の「特上鰻重」食べ比べ!贅沢ですね〜 モチロン美味かったです!
|

表参道 |
江戸時代から門前町として栄え、
当時の名残をとどめています
 |

成田山総門 |
開基1070年の記念事業により
2008年建立
高さ15mの総欅造り
 |

仁王門 |
1831年に再建
大提灯には大きな文字で「魚がし」
と書かれています
 |

大本堂 |
1968年建立
成田山で最も重要な
御護摩祈祷を行う中心道場。
 |

三重搭 |
1712年に建立。
塔には鮮やかな色彩の彫刻
「十六羅漢」が施されています
 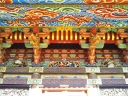 |

一切経堂 |
1722年に建立
堂内の輪蔵には一切経(約2,000冊)
が納められています
 |

鐘楼 |
1701年に建立
母屋造の銅板葺で袴腰をつけ
軒は和様二重
 |

聖徳太子堂 |
1992年に建立
日本の仏教興隆の祖である
聖徳太子の理念にもとづき
世界平和を願って建立
 |

釈迦堂 |
1858年に建立
かつての本堂
江戸時代後期の特色をよく残している
総欅づくりの御堂
 |

光明堂 |
1701年に建立
釈迦堂の前の本堂
大日如来、愛染明王、不動明王が奉安
  |

額堂 |
1861年に建立
絵馬や奉納額を掲げる建物
江戸時代に納められた絵馬や彫刻
 |

平和の大塔 |
1984年に建立
総高58m
真言密教の教えを象徴する塔
 |

出世稲荷 |
出世稲荷大明神が祀られています
本堂に安置される
御本尊の「荼枳尼天」
 |

成田山公園 |
東京ドーム約3.5個分の広さ
全ての生命を尊ぶという思想から
尊い生命をはぐくむ場となっています
 |